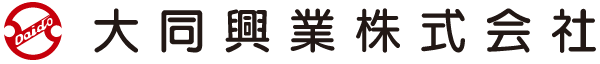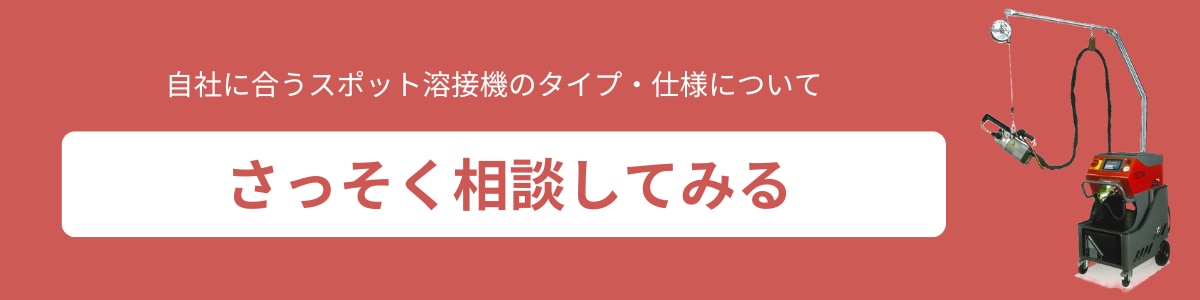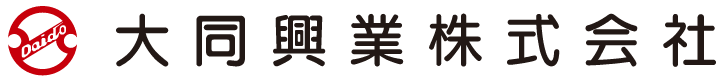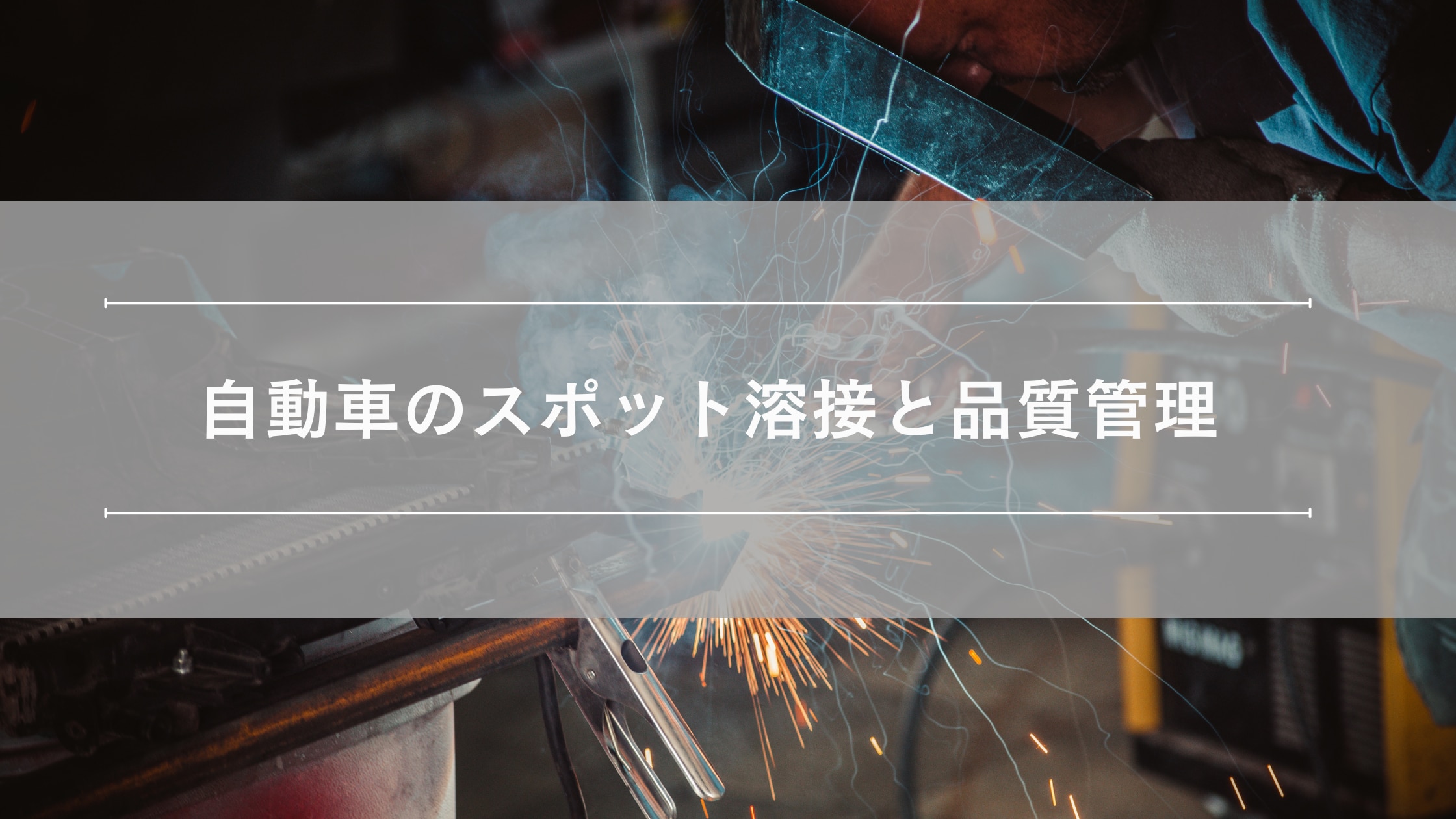
自動車のスポット溶接、正しくできてる?基本手順と品質管理のポイント
近年の自動車は、高張力鋼板やアルミ、樹脂など様々な素材で構成され、複雑な構造をしています。そのため、自動車鈑金におけるスポット溶接は、高い技術と品質管理が求められる作業となっています。
この記事では、自動車鈑金におけるスポット溶接の課題と、品質管理を行う上でのチェックポイント、機器選定のポイントについて解説します。
目次[非表示]
- 1.自動車鈑金における溶接の変化と課題
- 1.1.高張力鋼板や複合材の増加
- 1.2.メーカー指定・保険対応
- 1.3.修理工程の短納期化
- 1.4.溶接作業者の不足とばらつき
- 2.スポット溶接を行う際の注意点
- 3.品質管理を行うためのチェックポイント
- 4.スポット溶接機を選定する際のポイント
- 4.1.電流制御の精度と安定性(インバータ方式)
- 4.2.電極アームや二次側ケーブルの冷却方式
- 4.3.認証・規格への対応
- 5.スポット溶接機の導入事例
- 5.1.東洋ボデー株式会社様
- 5.2.株式会社金子自動車様
- 6.まとめ
自動車鈑金における溶接の変化と課題
高張力鋼板や複合材の増加
自動車の軽量化・高強度化に伴い、高張力鋼板やアルミ合金といった様々な金属材料の使用が増加しており、一部では樹脂系の複合材料も採用されています。
これらの金属材料は、従来の鋼板とは異なる溶接特性を持つため、適切な溶接条件の設定が難しく、高度な技術が求められます。
メーカー指定・保険対応
自動車メーカーは、車種ごとに修理方法を指定しており、特にスポット溶接に関しては、使用する機器や溶接条件、品質基準が厳格に定められています。また、保険修理の場合も、保険会社の基準に適合した修理を行う必要があります。
これらの基準を満たすために、自動車整備工場では常に最新の技術情報を入手し、適切な機器と溶接条件を選択する必要があります。
修理工程の短納期化
顧客ニーズの多様化に伴い、修理工程の短納期化が求められています。
溶接工程は車体修理において重要な工程であるため、作業の効率化は、全体の修理期間短縮に大きく貢献します。
そのため、高性能な溶接機を導入したり、作業手順を見直したりするなど、様々な工夫が必要です。
溶接作業者の不足とばらつき
熟練した溶接作業者の不足は、自動車鈑金業界全体の課題となっています。また、作業者によって溶接技術にばらつきが生じる可能性があるため、品質の安定化が重要な課題となっています。作業者への教育訓練の徹底や、溶接品質を数値で管理できるシステムの導入などが有効な対策となります。
スポット溶接は抵抗溶接、抵抗スポット溶接とも呼ばれ、電気抵抗によるエネルギーで接合する溶接です。
スポット溶接の基本、アーク溶接やレーザー溶接との違いについては下記の記事で解説していますので合わせてお読みください。
▼関連記事はこちら▼
スポット溶接を行う際の注意点
高品質なスポット溶接を行うためには、溶接条件の設定や、溶接後の確認作業が重要です。
適正な通電時間・電流・加圧力(三大条件)
スポット溶接の品質は、通電時間、電流、加圧力の三大条件によって大きく左右されます。
これらの条件は、溶接する母材の材質や板厚、形状、表面状態、溶接機の種類などによって最適な値が異なります。そのため、溶接前に必ずテストピースを作成し、適切な条件を決定する必要があります。
通電時間
溶接部に熱を供給する時間のことを指します。
通電時間が長すぎた場合、ナゲット(溶接部)が過熱し、溶接強度が低下してしまうことがあります。
逆に通電時間が短すぎると、ナゲットが小さく溶接強度が不足してしまうことがあります。
電流
溶接部で発生する熱量を決定します。
電流が大きすぎるとナゲットが大きくなりすぎたり、散りが発生したりする可能性があります。
逆に電流が小さすぎるとナゲットが小さく、溶接強度が不足することがあります。
加圧力
電極を母材に圧着する力のことを指します。
加圧力は母材を密着させ、電流を効果的に流すために必要です。加圧力が大きすぎるとナゲットは小さくなり、接合力は減少します。
逆に加圧力が小さすぎるとスパッタが発生して引っ張り強度を損なう可能性があります。
ナゲット径や押し痕の確認
スポット溶接の品質を確認するためには、ナゲット径と押し痕の深さを測定する必要があります。
ナゲット径は、溶接強度と直接関係しており、JIS規格などで規定されている下限値を満たしている必要があります。押し痕の深さは、母材の変形量を示す指標であり、深すぎると母材の強度が低下する可能性があります。
高張力鋼板/アルミ車体など材質ごとの注意点
高張力鋼板は、溶接時の熱影響を受けやすく、強度が低下する可能性があります。そのため、適切な溶接条件を設定し、熱影響を最小限に抑えることが重要です。
アルミは、熱伝導率が高いため、溶接時の熱が急速に拡散し、溶接不良が発生しやすい材料です。そのため、高出力の溶接機を使用したり、溶接速度を速めたりするなどの工夫が必要です。
部位ごとのスポット配置と補強構造への配慮
自動車ボディには、強度が必要な部分と、そうでない部分があります。そのため、スポット溶接を行う際には、部位ごとの強度要件を考慮し、適切なスポット配置と溶接ピッチを設定する必要があります。
また、補強構造がある場合は、その構造に影響を与えないように溶接を行う必要があります。
品質管理を行うためのチェックポイント
スポット溶接の品質管理は、最終製品の安全性に直結する重要な工程です。
自動車メーカーや車種、車両部位、板厚や材質によって設定値は変動するため、それぞれの基準値を確認し、それに合った溶接を行うことが重要です。
くぼみの深さ
電極の押し付けによって生じるくぼみの深さは、0.2~0.5mm程度が一般的ですが、自動車メーカーや補修のマニュアルにより異なります。深すぎる場合は、母材の板厚が薄くなり、強度が低下する可能性があります。専用のゲージを用いて正確に測定し、基準値を超えていないか確認しましょう。
JISや車体メーカー基準に基づくナゲット径の目安は以下の通りです。
鋼板の板厚(t) | 最小ナゲット径の目安(mm) |
t = 0.8 mm | 約 5.0 mm |
t = 1.0 mm | 約 6.0 mm |
t = 1.2 mm | 約 7.0 mm |
t = 1.6 mm | 約 8.0 mm |
※実際の数値はメーカーや部位(外板・フレーム)によって異なるため、必ずサービスマニュアルや修理要領書を確認してください。
ナゲット径は溶接強度と相関があり、JIS規格で規定されている下限値を満たす必要があります。母材の材質や板厚によって適切なナゲット径は異なるため、事前にテスト溶接を行い、最適な溶接条件を決定し、その条件で溶接したナゲット径を確認しましょう。
溶接部の割れ
溶接部には、溶接時の熱影響や応力集中によって割れが発生することがあります。目視検査を行い、割れの有無を確認する必要があります。割れは強度低下の原因となることがあります。
▼確認のタイミング
溶接直後 | 過熱割れ・表面欠陥の有無 |
冷却後・成形後 | 再熱割れや表面割れの確認 |
塗装前 | シーラー前に最終確認、割れがあると再作業が必要 |
検査記録として | 写真記録・検査表への記入を実施(保険修理時など) |
ナゲット溶け込み率
ナゲット溶け込み率は、溶接部の断面におけるナゲットが占める割合を示す指標です。
溶け込み率が低いと、溶接強度が不足する可能性があります。断面検査を行い、溶け込み率が基準値を満たしているか確認しましょう。溶け込み率の詳細は車種や部位ごとの修理基準書(メーカー指示)を参考にしてください。
スポット溶接機を選定する際のポイント
品質管理を徹底するためにも、適切な機能を備えた溶接機を選定することが重要です。
電流制御の精度と安定性(インバータ方式)
スポット溶接では通電時間・電流・加圧力( 三大条件)のバランスが重要ですが、特に電流制御の精度が品質に直結します。
インバータ方式の溶接機は、電流を細かく制御できるため、母材の厚みや材質に応じた、安定したナゲット形成が可能です。品質管理を重視する現場では、インバータ方式が今や標準となりつつあります。
電極アームや二次側ケーブルの冷却方式
スポット溶接機は高電流を流すため、電極アームや二次側ケーブルが非常に熱くなります。そのため、効率よく熱を逃がすことが品質に大きく影響します。
特に水冷式は熱をしっかりと抑え、電極の温度上昇を防ぐことで安定した溶接品質を実現。連続作業でもナゲット径が安定し、電極の摩耗も減らせるため、メンテナンス頻度も低くなります。
一方、空冷式はコストは抑えられますが、熱による品質のばらつきや電極の消耗が早まるリスクがあります。品質を重視する現場では、水冷式を選ぶことが推奨されます。
認証・規格への対応
溶接条件が一層厳しくなることや、車両のボディ剛性がさらに高まっていくことが予想されており、これに対応するには、現時点の要求を満たすだけでなく、将来的な基準にも余裕を持って対応できる溶接能力を備えた機種を選定することが重要です。
TECN社製のスポット溶接機は選定する際のポイントをクリアしており、今後も厳しくなるであろう自動車整備の溶接条件に対応する能力と剛性を搭載しております。
詳しい製品情報はこちらよりカタログをダウンロードしてご確認ください。
スポット溶接機の導入事例
ここでは、スポット溶接機を導入し、品質や作業効率を向上させた企業様の事例を紹介します。
東洋ボデー株式会社様
東洋ボデー㈱様は鈑金塗装工場認証基準の最高ランクにあたる「TUVプラチナ認証」を取得されています。スポット溶接機を含む、最新鋭の設備を導入し車のボディや材質、溶接条件の進化に常に対応できる環境のため、お客様に自信をもって安心と安全を提供されています。
▼事例をチェックしてみる▼
株式会社金子自動車様
㈱金子自動車様の鈑金塗装の評判は同業他社からも高く、丁寧な仕事が評価されています。その結果、高級外車ディーラー「YANASE」の協力工場にも選ばれています。さらに、「1オーナー修理永久保証」を掲げ、修理した部分に関しては最後までサポートする体制を整えており、お客様に安心を提供されています。
▼事例をチェックしてみる▼
スポット溶接機をお探しのご担当者様へ
まとめ
高品質なスポット溶接は、顧客からの信頼獲得に繋がり、ひいては企業のブランドイメージ向上に貢献します。高性能な溶接機を導入することで、溶接品質の向上と作業効率の向上が期待できます。溶接機を選ぶ際には、品質管理機能についても十分に検討しましょう。